top of page

ブログ


仕事への誇りと心配りがなぜ大切か:プロフェッショナリズムの「活力サイクル」
あなたの仕事は「消耗」と「活力」のどちらを生んでいますか?日本の空港清掃員が実践する「生きがい(Ikigai)」の精神に学び、仕事への「誇り」と「心配り」が、個人と組織を活性化する「活力サイクル」をどう生み出すかを考察します。単なる義務ではなく、人としての選択が世界を変える。
2025年10月23日


スコアボードの向こう側:シドニー大学の未来のリーダーたちから学ぶこと
シドニー大学で、30人の多様な学生たちと3時間過ごし、あるシミュレーションの指導をしました。彼らは当初、ルールに縛られていましたが、すぐに自分たちでルールを作れることに気づきました。ある学生が勇気を出して、部屋の反対側にいる別のグループに話しかけに行った小さな行動が、波紋を広げました。その結果、それまでの競争的な議論は、協力して共通のビジョンを描くものへと変化していったのです。
2025年10月8日


「子どもたちの可能性は無限大」ーポッシブルワールドが教えてくれた場の力
子どもたちの「未熟さ」は、無限の可能性を秘めた最大の強みです。大人は自分の経験を基準にしがちですが、彼らの何にも染まらない心こそが、世界に貢献できるパワフルなエネルギーの源泉なのです。
先日、私が提唱する「場づくり」の理念を体現するプログラムに参加しました。予期せぬ状況の中、子どもたちと「同じ目線」で向き合うことを決意。その姿勢が、彼らの心を開き、秘めた力を引き出す鍵だと実感しました。
この経験で強く感じたのは、子どもたちのありのままの姿を引き出す「場」の力です。最終発表で彼らが見せてくれたのは、等身大の自信と社会への貢献意欲。自分の中に眠る光を見つけ、一歩踏み出す勇気を得たのです。
私たち大人は、子どもたちが自分らしく輝ける「場」を創造し続ける役割を担っています。今回の経験から、この揺るぎない第一歩は、子どもたちと同じ目線で向き合う姿勢なのだと、改めて強く感じました。
2025年9月1日


父とコーヒーとフランス語とマナビ
90歳の父との暮らしは発見に満ちている。父は「覚えられない」と笑いながら毎日フランス語に向き合う。その姿は「学ぶ」行為自体が日常を彩ることを教えてくれる。
そんな父にコーヒーの淹え方を教えた時、うまくできない姿に、つい「私がやった方が早い」と思ってしまった。子の学びが常に「正の傾き」で伸びるのに対し、高齢者の学びは結果に繋がりにくい。だが「どうせ忘れるから」と機会を奪うのは、学びの本質を見誤っているのだと、娘に教えた数学の話から気づかされた。
真の価値は、結果という物差しでは測れない「できた!」という一瞬の喜びと、人と人とが関わり合う「過程」そのものの豊かさにある。この気づきを胸に、後日父の通院を見守った。すると父は様々な手続きを一人でこなし、「俺、結構できるじゃないか」と誇らしげに笑ったのだ。
父の後ろ姿は、たとえすぐに忘れてしまうとしても、その一瞬の輝きを尊重し、学びの機会を奪わないことの尊さを、静かに示している。
2025年8月15日


日本文化が世界に問いかける「関係性」の美学
西洋的な個人主義が主流の現代において、日本文化が世界に問いかけるものとは?それは、日本語の「聞き手責任」や「人間」という漢字に込められた「関係性」の概念に深く根差しています。目には見えにくい「間」の感覚が、なぜ日本の社会や個人のあり方に大きな役割を果たすのか。その奥深さに触れてみませんか?
2025年7月31日


競争から共創へ──マーケティングのパラダイムシフト
近年、マーケティングの世界において「共創(co-creation)」という言葉が注目されています。
かつては「競争に勝つ」「ターゲットを攻略する」といった戦略思考が主流でしたが、いま求められているのは、顧客とともに価値を育てていく視点です。
2025年7月7日
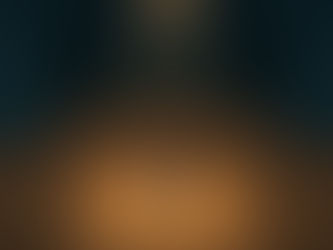

ゲームの中でペルソナ体験をしたら、世界の見え方が変わった
発想の転換を促すオンラインゲームコンテンツ「ポッシブルワールド」では、参加者が“なりたい誰か”を演じることがあります。
それは、現実での肩書きでも性格でもありません。
「本当はこんなふうに動いてみたい」「こんな人になってみたい」という気持ちに、少しだけ素直になってみる。
そんな遊び心が、あちこちで息づいています。
2025年5月23日


平均点より「ウェルビーイング」?教育の本質を問い直す
「平均点を上げるように」
これは、学校現場ではよく聞かれる言葉です。
成績を上げること、数値で見える成果を出すことが、教育の目的であるかのように。
でも、ふと立ち止まって思うんです。
本当にそれだけが、子どもたちの「学び」なのでしょうか?
2025年5月16日


何もないから生まれる:余白が導く創造とつながり
なぜ、今「余白」が必要なのか?
現代社会は、常に成果を求められ、スピードが重視される環境が当たり前となっています。そのような中で、人々が「息苦しさ」や「閉塞感」を抱くケースが増えています。
こうした社会のあり方に対し、「何もない空間=余白」が持つ力に着目する動きがあります。ポッシブルワールド・ラジオ「#47 目的を手放す勇気と、そこにある可能性」の中で、創造やつながりの可能性は、むしろ何も定義されていない空間にこそ宿る、という話がありました。
2025年5月15日


学校に地域がやってくるーーただ“そこにいる”ことの価値
かつての子どもたちは、空き地や駄菓子屋、公園など、特に目的もなく集える場所で自然と人と関わることができました。
そこには、偶然の出会いと関係性の中で、教え合いでも競争でもない豊かな学びがありました。
しかし現代では、安全性や効率性が優先され、そうした「ただそこにいる」場所が少なくなっています。
子どもが地域の大人と出会う機会も減り、教育の現場でも、目的と成果が前提となる関係性が中心になっています。
偶然から始まる学びの余白が、静かに失われつつあります。
2025年5月13日
bottom of page

